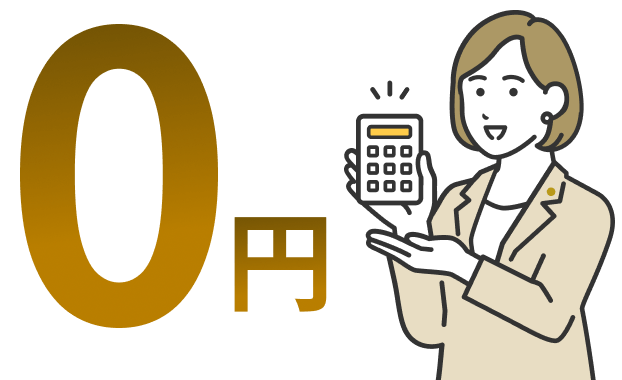生前贈与の注意点とは? よくある失敗例とともに弁護士が解説
- 遺産を残す方
- 生前贈与
- 注意点

浜松市の統計によりますと、令和元年は市内で8447人の方が亡くなっています。この数字が意味するところは、これに近い件数の相続が発生しているということです。人は誰でも死ぬことが避けられない以上、相続も避けて通れません。
しかし、相続は相続人(亡くなった方の財産を受け取る人)にだけ任せておけばよいというものではありません。残された遺族が円満に相続財産を承継するためには、被相続人(亡くなった人のこと)による生前の相続対策が何よりも重要なのです。相続対策はさまざまなものがありますが、代表的な方法のひとつとして「生前贈与」があります。
しかし生前贈与の仕組みは複雑であり、活用の仕方を間違えると相続対策として失敗してしまうこともあります。そこで本コラムでは、代表的な生前贈与とその活用に失敗しないようにするための注意点について、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。
1、生前贈与の代表例
生前贈与とは、生きているうちに自身の財産を後の世代に無償で譲ることです。贈与された側からみると、生前贈与は受け取った時点の経済的恩恵だけではなく相続が発生したときの相続税対策にもなり得ます。
相続税は被相続人(亡くなった人のこと)の相続発生時の相続財産額に比例して高くなる仕組みです。したがって、相続が発生する前に、自身の財産を、相続人と推定される方に贈与して相続開始時点での財産額から分離しておくことによって、相続税を低くすることができるのです。
生前贈与の方法は、さまざまなものがあります。ここでは、代表的な生前贈与の方法についてご紹介します。
-
(1)暦年贈与
暦年贈与をはじめとする生前贈与でポイントとなる贈与税とは、財産をあげる人(贈与者)から財産をもらう人(受贈者)へ財産の贈与があったときに、財産をもらう人に対して課される国税のことです。
「暦年贈与」とは、その年の1月1日から12月31日までに受けた贈与の合計額が110万円に満たない場合は、贈与税が課税されず申告も不要とする制度です。暦年贈与には、贈与者と受贈者に特段の制限は設けられていません。したがって、血縁関係がない第三者に対する贈与でも活用することができるのです。 -
(2)相続時精算課税制度
「相続時精算課税制度」とは、相続が発生したときに相続人が被相続人から受け取る予定の財産を被相続人の生前に受け取っておくことで、贈与税を最大2500万円まで非課税とすることができる制度です。
暦年課税制度と比較して、相続時精算課税制度では贈与税の非課税枠が2500万円と大きいことが特徴です。そのため、相続人の不動産取得資金や事業承継の一環として中小企業オーナーが自分の子どもや孫に自社株式を贈与するなどの場合に多く活用されているようです。
相続時精算課税制度では2500万円を超過する分の贈与に対しては一律20%の贈与税が課税されます。贈与税の最高税率が55%であることを考えると、大きな節税効果が期待できるといってよいでしょう。また、相続発生時の財産額と相続時精算課税制度を用いた贈与の合計額が相続税の基礎控除(3000万円+法定相続人の人数×600万円)の範囲内に収まる場合は、とても有効な節税対策となり得ます。なお、2500万円の贈与税非課税枠は、一度に贈与しても複数回以上に分割して贈与しても問題ありません。
相続時精算課税制度における対象者は、贈与が行われる年の1月1日現在で60歳以上の受贈者の親または祖父母です。また、受贈者は贈与が行われる年の1月1日現在で20歳以上の子どもまたは孫です。
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、受贈者が「相続時精算課税選択届出書」を贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書に添付して税務署に提出しなければなりません。このとき、受贈者は贈与者を父・母・祖父・祖母の中から選択することができます。つまり、父からの贈与は相続時精算課税制度を活用する一方で、祖父からの贈与は暦年贈与制度を活用するということもできるのです。ただし、特定の贈与者に対して相続時精算課税制度を選択すると、相続が発生するまでは暦年課税制度に変更することができないという点に注意が必要です。
相続時精算課税制度を適用することにより、受贈者が負担する贈与税は低くすることができます。しかし、相続税は相続時精算課税制度が適用された贈与財産に対して課税されます。相続が発生したとき、相続税は相続時精算課税制度の適用を受けて贈与された財産と受けていない相続財産を合算して計算されます。
このとき、相続時精算課税制度が適用される財産に贈与税が課せられていた場合、その贈与税額に相当する金額を相続税総額から控除します。相続税総額からその金額を控除しきれない金額があるときは、相続税の申告書を提出することによりその相当額について贈与税の還付を受けることが可能です。 -
(3)住宅取得等資金の贈与税の非課税特例
「住宅取得等資金の贈与税の非課税特例」とは、令和3年12月31日までに受贈者が父母や祖父母から住宅取得資金等の贈与を受けたとき、最大3000万円の非課税限度額までは贈与税が課税されない制度です。
この特例を受けるためには、受贈者の所得は2000万円未満であること、新築する家屋の総面積は50平米以上240平米以下でなければならないなどの制限があります。また、非課税限度額は土地と家屋を取得する契約を締結した日や、家屋が省エネルギー等基準に適合するか否かにより変わるため、注意が必要です。 -
(4)教育資金の一括贈与
令和3年3月31日までに行われる30歳未満の子どもや孫の教育資金を一括して贈与することに対しては、1500万円まで贈与税が発生しないという特例が設けられています。これにより、一世代をまたいでまとまった金額を生前贈与することや、3年以内の生前贈与加算額について贈与税の課税対象外とすることができます。特に、孫を持つ祖父母にとっては自分の意思で孫に教育資金という重要なお金を贈与することができるという点で、大きなメリットがあります。
2、生前贈与でよくある失敗事例
生前贈与でよくある失敗事例として代表的なものは、制度や法解釈の誤りにより制度の特例を受けられないことや、その結果相続税額が贈与税額を上回ってしまうことです。
以下では、代表的な生前贈与の方法における失敗事例についてご紹介します。
-
(1)暦年贈与の失敗例
暦年贈与は、贈与者の受贈者に対するまとまった金額を小口に分けて贈与することを、国税当局が奨励するものではないといわれています。
たとえば、暦年贈与特例を用いて子どもに毎年110万円ずつ20年間コンスタントに贈与を続けたとします。この場合、贈与者は暦年贈与ではなく「連年贈与」として最初から合計2200万円贈与する意図があったとみなされ、贈与した合計額2200万円に対して贈与税が課税されてしまうことがあるのです。 -
(2)相続時精算課税制度の失敗例
相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額は、その適用を受けていない相続財産と合算されます。そのときに合算される相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産の価額贈与時は、相続発生時における当該財産の時価です。つまり、相続時精算課税制度の適用によって有価証券や収益不動産の贈与を受けていたとしても、相続発生時において贈与を受けたときよりも当該資産の評価額や時価が下落していた場合は、適用を受けていなかった場合とくらべて相続税が割高となってしまうのです。
また、相続時精算課税制度で現金の贈与を受けていた場合、それを相続開始時までに使い込んでしまった場合は、相続税納税資金が足りなくなってしまうことがあります。 -
(3)住宅取得等資金の贈与税の非課税特例の失敗例
この特例では、受贈者は贈与者の直系卑属、つまり受贈者の実の子または孫でなければならないと定められています。たとえば、実の娘の配偶者である義理の息子名義で住宅を購入するときに義理の息子へ購入資金を贈与したとしても、この特例を受けることはできないのです。もっとも、購入する住宅を実の娘と義理の息子さまの共有名義にした場合は、娘の持ち分に対する贈与ということで、本特例の適用を受けることが可能です。
また、本特例を受けるための条件として「贈与を受けた翌年の3月15日までにその家屋に居住することが確実と見込まれること」と規定されています。さらに「贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない場合は、この特例の適用を受けることはできない」とも規定されています。たとえば、子どもまたは孫が親または祖父母からの贈与資金により自宅を購入したとします。しかし、建築・引き渡しまでに海外に転勤するなどの理由で翌年末まで一度も当該自宅に住むことがなかったときは、本特例の適用を受けることはできないのです。 -
(4)教育資金の一括贈与の失敗例
教育資金の一括贈与における非課税特例は、あくまで教育目的の資金の贈与が対象です。
たとえば、子どもや孫が大学まで進学することを見越して教育資金を贈与していたとしても、何らかの理由で大学まで進学しなかった場合は、その余ったお金について贈与税が課税されることになります。このような場合、暦年贈与を活用していた方が相続税対策上有効だったということになります。
3、まとめ
生前贈与に限らず、相続対策は法的な知見と経験を要するものです。誤った相続対策は、かえって相続人の負担を増やすことになりかねません。したがって、生前贈与などの相続対策を講じるときは弁護士や税理士に依頼することをおすすめします。
相続全般について知見のある弁護士に依頼すれば、円満な相続に必要なアドバイスはもちろんのこと、財産調査や遺言書の作成、さらには相続が発生したあとの遺言執行者(遺言の内容を実現する人)の役割を任せることができます。
生前贈与など相続対策をご検討のときは、ぜひベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士までご相談ください。ベリーベスト法律事務所のグループ法人の税理士と力を合わせ、あなたの相続対策のために、ベストを尽くします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています