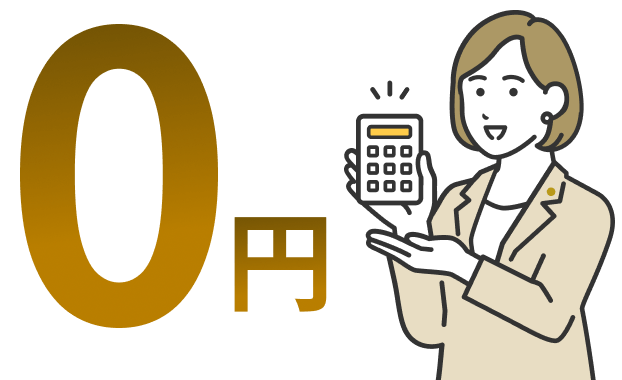相続(遺産分割)のやり直しはできる? 可能なケースと時効や注意点
- 遺産を受け取る方
- 相続
- やり直し

ご家族が亡くなると相続手続きが始まります。静岡県浜松市が毎月ホームページで公開している「推計人口表、人口動態」によると、令和7年4月1日時点における出生者数は319名、対して死亡者数は864名と、自然動態としては減少しており、相続が始まったという話を耳にすることは多いのではないでしょうか。
トラブルにならず相続手続きが終わればよいのですが、相続財産を相続人の間で分け合う「遺産分割」の結果に納得できないまま、手続きが完了してしまうケースがあります。相続手続きをやり直せるケースは限られていますが、やり直しが認められる可能性はゼロではありません。
本記事では、相続手続きのやり直しが認められるケースや、やり直す際の手順・注意点などをベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。相続手続きをやり直したい方は、弁護士に相談してその可能性を模索することをおすすめします。


1、相続手続きのやり直しはできる?
相続手続きが開始されると、相続人や相続財産の確定を経て、相続財産を相続人の間で分け合う「遺産分割」を行うことになります。
遺産分割には、特に期限が設けられておらず、下記いずれかに該当した場合に、遺産分割は完了します。
- 相続人全員の間で遺産分割協議書を締結した場合
- 遺産分割調停が成立した場合
- 家庭裁判所の遺産分割審判が確定した場合
遺産分割が完了すると、原則として遺産分割をやり直すことはできず、相続手続きを進めていくことになります。
ただし、例外的に遺産分割のやり直しが認められるケースもあります。
遺産分割の内容に納得できない方は、やり直しが認められる余地がないかどうか、弁護士に相談してアドバイスを求めましょう。
2、遺産分割のやり直しが認められるケース
遺産分割のやり直しが認められるケースは6パターンあります。
(2)一部の相続人が遺産分割に参加していなかった場合
(3)一部の相続人に意思能力がなかった場合
(4)利益相反のある未成年者の相続人について、特別代理人を選任しなかった場合
(5)錯誤・詐欺・強迫によって遺産分割を取り消せる場合
(6)分割していない新たな遺産が判明した場合
では、各項目について詳しく見ていきましょう。
-
(1)やり直しについて相続人全員が合意した場合
遺産分割によって取得した財産を、すべての相続人が持ち寄って再び分け合うことは自由です。
したがって、相続人全員が合意した場合は、遺産分割をやり直すことができます。 -
(2)一部の相続人が遺産分割に参加していなかった場合
分割前の遺産は、すべての相続人の共有財産です(民法第898条)。したがって、すべての相続人が参加しなければ遺産分割はできません(民法第251条)。
遺産分割に参加していない相続人が1人でもいれば、その遺産分割は無効です。この場合、遺産分割をやり直す必要があります。 -
(3)一部の相続人に意思能力がなかった場合
遺産分割に対して同意を与えるためには、意思能力が必要です。意思能力とは、自らの行為の結果を判断できる能力をいいます。認知症の進行などにより、意思能力を欠いた状態で遺産分割に同意しても、その同意は無効です(民法第3条の2)。
1人でも意思能力を欠いた状態の相続人がいれば、遺産分割全体が無効となり、やり直しが必要になります。
遺産分割をやり直す際には、意思能力を欠いた状態にある相続人については、家庭裁判所に後見人の選任を申し立てなければなりません。 -
(4)利益相反のある未成年者の相続人について、特別代理人を選任しなかった場合
未成年者である相続人については、法定代理人が代わりに遺産分割へ参加することになります。
未成年者の法定代理人は親であるのが一般的ですが、親も子どもとともに相続人であるケースが少なくありません。たとえば、父親が亡くなり、母親と未成年者の子どもが相続人であるようなケースです。
この場合、子どもと親の利益が相反する関係(利益相反)になるため、子どものために特別代理人を選任する必要があります(民法第826条第1項)。
特別代理人の選任が必要であるにもかかわらず、特別代理人を選任しないまま法定代理人が未成年者の代わりに遺産分割へ同意した場合、その同意は無効であるため、遺産分割のやり直しが必要になります。 -
(5)錯誤・詐欺・強迫によって遺産分割を取り消せる場合
遺産分割への同意が以下のいずれかに該当する事情により行われたときは、表意者はその同意を取り消すことができます。
-
錯誤(民法第95条)
遺産分割に関して重要な錯誤(=勘違い)があった場合には、遺産分割への同意を取り消すことができます。
ただし、動機の錯誤(法律行為の基礎とした事情についての認識の誤り)による取り消しには、その動機が他の相続人に対して表示されていたことが必要です。また、錯誤について表意者に重大な過失があったときは、原則として取り消しが認められません。 -
詐欺(民法第96条)
他人にだまされて遺産分割に同意した場合には、その同意を取り消すことができます。
第三者による詐欺の場合には、他の相続人全員がその事実を知り、または知ることができた場合に限り、遺産分割への同意を取り消すことができます。 -
強迫(民法第96条)
他人から暴力を受け、または脅されたことにより遺産分割に同意した場合には、その同意を取り消すことができます。
ただし、錯誤・詐欺・強迫による取消権を行使には期限があるため注意が必要です(民法第126条)。
- 追認をすることができるとき(=取り消しの原因となった状況が消滅し、かつ取消権を有することを知ったとき)から5年間
- 遺産分割に同意したときから20年間(民法第126条)
-
錯誤(民法第95条)
-
(6)分割していない新たな遺産が判明した場合
遺産分割の際には判明していなかった遺産が、後から判明するケースもあります。
遺産分割時に後から判明した遺産の処理方法を合意していれば、その内容に従って相続する人を決めます。
これに対して、後から判明した遺産の処理方法について合意していない場合や、合意した方法では相続する人が決まらない場合には、その遺産について改めて遺産分割を行う必要があります。
3、遺産分割のやり直しができないケース
協議・調停・審判によって確定した遺産分割は、やり直しが認められないのが原則です。
前述のように、遺産分割が無効とされる場合や取り消し得る場合、または新たな遺産が判明した場合などでなければ、遺産分割のやり直しは認められません。
唯一、相続人全員が合意した場合に限り、その他の条件にかかわらず遺産分割をやり直すことができます。ただし後述するように、余分な課税が発生するなどのデメリットが生じ得る点に注意が必要です。
4、遺産分割をやり直す場合の手順
遺産分割をやり直す際には、手順を追って対応しなければなりません。なお、弁護士に依頼すると、すべての手続きを対応してもらうことができます。
まずは、他の相続人に対して遺産分割のやり直しを提案します。
無効原因または取消原因がある場合は、その内容と根拠を示して、遺産分割をやり直す必要があることを説明しましょう。
② 遺産分割協議の再開・遺産分割協議書の締結
遺産分割のやり直しについて他の相続人の同意が得られたら、遺産分割協議を再開します。
遺産分割の内容に合意したら、その内容を遺産分割協議書にまとめて締結しましょう。
③ 遺産分割調停
遺産分割協議がまとまらない場合や、他の相続人が遺産分割のやり直しに同意しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。
調停委員が仲介者となり、すべての相続人の主張を聞き取ったうえで、歩み寄りを促すなどして合意形成をサポートします。
④ 遺産分割審判
遺産分割調停が不成立に終わった場合は、家庭裁判所が審判によって遺産分割の内容を決定します。
5、遺産分割をやり直す場合の注意点
遺産分割をやり直す際に、特に注意するべきポイントが2つあります。
-
(1)遺産分割のやり直しは第三者に対抗できない
遺産分割をやり直しても、第三者の権利を害することはできません(民法第909条ただし書)。
たとえば1回目の遺産分割の後で、不動産を相続した人が第三者にその不動産を譲渡したとします。この場合、当該第三者から不動産を返してもらうことはできません。
遺産分割の完了から時間がたっていると、第三者への譲渡等によって取り戻せない遺産が増えることが想定されます。遺産分割のやり直しは早めに着手しましょう。 -
(2)余分な課税が発生することがある
相続人全員の合意に基づいて遺産分割をやり直すときは、新たに贈与または譲渡がなされたものとして取り扱われます(相続税法基本通達19の2-8ただし書)。
この場合、贈与税や所得税・住民税が余分に課されることがあります。
さらに、遺産分割のやり直しによって不動産を相続する人が変わる場合は、相続登記手続きを行う際に、改めて登録免許税が課される点にも注意が必要です。
6、まとめ
確定した遺産分割のやり直しは原則として認められませんが、ここまで解説したとおり、無効事由または取消事由がある場合や、新たに遺産が判明した場合には、やり直しが認められることがあります。
また、相続人全員が合意した場合にも、遺産分割のやり直しが可能です。
遺産分割をやり直す際には、慎重な事前検討と対応が必要になるため、弁護士に依頼することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は、遺産相続に関するご相談を随時受け付けております。遺産分割の結果に納得できず、やり直したいと考えている方は、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています