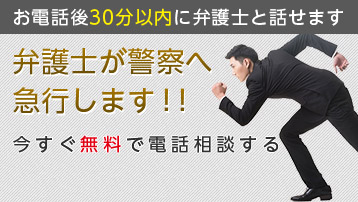山火事で問われうる罪とは? 失火と放火による違いととるべき対応
- その他
- 山林
- 放火

「静岡県森林・林業統計要覧 令和5年度版」によると、浜松市内の森林面積の割合は県平均とほぼ同じですが、人工林率は76.74%と県の平均58.85より高いことがわかっています。
さらに、静岡県が公表するデータによると、山火事の発生原因は、たき火・火遊び・放火・たばこなどとなっており、人為的な要因による物が大半を占めています。山林には枯れ草や枯れ枝などの燃えやすい物が多いことから、広範囲での山火事が起こりやすいものです。ひとたび山火事になれば、被害が大きくなるケースが多く、山火事を起こした方が放火の容疑で逮捕される可能性があるでしょう。
本コラムでは、山林に放火した場合や誤って火事になってしまった場合について、成立する犯罪から負うべき責任などについて、刑事事件についての知見が豊富なベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。


1、山林への放火は森林法違反にあたる
森林に放火することや、森林で誤って火事を起こしたことに対する刑罰は、「森林法」という法律に定められています。
森林法は、普段の生活であまりなじみのない法律なので、初めて聞いたという方も多いかもしれません。森林法は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、それによって国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする法律です。
森林放火罪については、刑の下限が2年以上の有期懲役となっており、重い刑が科せられます。自己の森林への放火については、少し刑の下限が低くなっています。
なお、森林で誤って火事を起こして場合については、懲役刑ではなく罰金刑となっています。
2、失火罪と放火は何が違う?
上記の森林法や、刑法などの刑事法でも、「放火」と「失火」については、区別して規定されています。
放火とは、わざと何かを燃やす行為をいいます。
失火とは、わざとではなく、不注意によって、何かを燃やしてしまう行為をいいます。
つまり、放火と失火は、故意か不注意かという点で違いがあります。
-
(1)放火に関する規定
放火についての代表的な規定は、刑法に定められている放火の罪が挙げられます。
放火の罪には、人が住んでいる住宅などに放火する現住建造物放火や、人が使っていない建物に放火する非現住建造物放火などの罪があります。現住建造物等放火
第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。現住建造物等放火の罪は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」であり、この後に紹介する非現住建造物等放火の罪と比べて、刑罰が重くなっています。その理由は、現住建造物等が火事になれば、非現住建造物等の火事と比べて、人の体や命に危害が及びやすいためです。
なお、「現に人が住居に使用」している建造物とは、人が日常的に生活の場として使用している物を指し、放火の時点で人が中にいなかったとしても現住建造物にあたります。
非現住建造物等放火に該当する場合には、他人の所有建物などに火をつけた場合には「二年以上の有期懲役」、自分の所有不動産などに火をつけた場合には「六月以上七年以下の懲役」となる場合があります。
なお、建物以外への放火については、建造物等以外放火罪という規定でまとめられています。たとえば、自動車、飛行機、バイクなどに放火する行為はこれにあたります。 -
(2)失火に関する規定
失火によって、人が住んでいる家や、人が使っていない建物を燃やしてしまう行為には、失火罪にあたります。失火罪については、50万円以下の罰金という刑罰が定められています。
なお、業務上の失火については、「三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金」という、より重い刑罰が定められています。 -
(3)その他火に関する犯罪
上記に紹介した物のほかにも、刑法には火に関する犯罪が定められています。
- 延焼罪(刑法第111条):自分が所有している非現住建造物・建物以外の物を燃やして、他の人の建造物や物に燃え広がってしまった場合に成立する犯罪です。
- 消火妨害罪(刑法第114条):火事が起こっているときに、消火器・消火用ホースなど消火用に使う物を隠す・壊すなどして、消火活動の邪魔をした場合に成立する犯罪です。
お問い合わせください。
3、山火事を起こした方が負う賠償責任(民事責任)は?
山火事を起こして、他の人に損害を与えてしまった場合には、刑事上の責任を問われて刑事裁判にかけられ、処罰を受ける可能性があります。もちろん刑事責任だけでなく、民事上の責任も問われ、損害賠償金を支払わなければならなくなる可能性が高いといえるでしょう。
-
(1)不法行為と失火責任法
たとえば、たばこの火が落ち葉や枯れ草などに燃え移る可能性があると認識しながら、わざと火が消えていないたばこのポイ捨てし、山火事が起こり、民家に燃え移ってしまい、全焼してしまったとします。
この場合、たばこをポイ捨てした人には、不法行為(民法第709条)が成立し、民家の持ち主に対して、民家が全焼してしまった分の損害を賠償しなければならない可能性があります。
しかし、故意の放火ではなく、過失の放火については、民法とは別に、特別な法律が設けてあります。それが、「失火ノ責任ニ関スル法律」です(失火責任法と呼ばれています)。
失火責任法では、民法709条の規定は失火の場合には適用されないが、失火をした人に重大な過失があった場合には適用されることが定められています。
つまり、「故意」でもなく、「重大な過失」とも言えない不注意で火事を起こしてしまった場合には、民法第709条を適用しない、つまり、損害賠償責任を負わなくてよいということです。 -
(2)失火責任法がなぜ成立したのか
なぜ不注意で火事を起こしてしまった場合には、不法行為責任を負わなくてよいのかというと、日本の家は木造家屋が多く、火事が起こると燃え広がって、損害額が莫大になってしまうことと、失火の際には失火を起こしてしまった人自身も焼け出されていることが多いことから、失火を起こしてしまった人の責任を免除する必要があるためと言われています。
もっとも、「重過失」で失火を起こしてしまった場合には、失火責任法による免責を受けることはできません。「重過失」とは、わずかの注意さえすれば、たやすく結果を予想できた場合であるのに、漫然とこれを見過ごしたような、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態をいいます。
たとえば、何らの対策をせずに寝たばこをして火事を起こしてしまった場合や、台所のガスコンロにてんぷら油が入った鍋を火にかけたまま、目を離してしまい、てんぷら油に引火して火事になってしまった場合に重過失が認められた裁判例があります。
お問い合わせください。
4、山火事を起こしてしまったら、まずは弁護士に相談を
たとえ一瞬の不注意であろうと山林火災を起こしてしまった場合は、大きな災害へと発展し周囲の人々に多大な被害をもたらしかねません。もし、あなたの不注意で山林火災を起こしてしまった場合は、森林法違反や失火罪などの刑事責任が問われるだけでなく、損害賠償金が請求される可能性もあり、民事的な責任を負う可能性が非常に高いでしょう。
万が一、山林で火事を起こしてしまったときは火災の状況を正確に把握し、消防署に連絡し、警察に相談しましょう。そのうえで、弁護士に相談することも検討すべきです。弁護士は、刑事弁護、民事訴訟、保険会社との交渉など、さまざまな問題に対応することが可能です。特に刑事事件になった場合は、早期に弁護士に相談することで、より良い解決策を見つけることができるでしょう。
ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスでは、刑事事件についての対応経験が豊富な弁護士があなたが過剰に思い罪が問われることの内容サポートします。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています