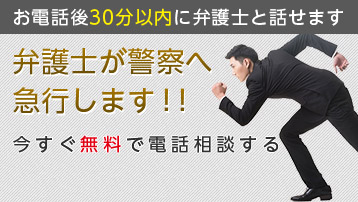共犯とは? 共犯で逮捕された場合の対処法や罪の重さを弁護士が解説
- その他
- 共犯とは

令和3年4月21日静岡地裁浜松支部で受給資格がないのにコロナ給付金をだまし取ったとして詐欺罪に問われている男性の刑事裁判が審理されました。報道によると、男性は知人らと共謀して給付金をだまし取ったほか、別の知人にも同様の手口で給付金をだまし取らせた疑いが持たれているとのことです。
コロナ給付金詐欺は全国でも摘発が相次いでおり、その多くは犯行の手口を伝授する指南役の関与が疑われています。また、指示役と末端の実行役など共犯者多数で犯行に及ぶ特殊詐欺も依然として多発しており、令和2年中の静岡県内における特殊詐欺の被害額は6億円にも達しました。
複数の共犯による犯罪は、組織的、計画的なものもありますが、中には現場に居合わせて犯罪に巻き込まれてしまうなど、さまざまなパターンがあります。
このコラムでは、
・共犯とはどのようなものか
・共犯の罪の重さはどのようにして決まるのか
・共犯として逮捕された場合の対処法
について弁護士が解説します。
(出典:静岡県警ホームページ)
1、共犯とは? どこまで罪に問われる?
共犯が問われる責任について
- 単独犯との違い
- 実行していない犯罪も罪に問われるのか
- 民事上の責任はどうなるのか
について解説します。
-
(1)単独で罪を犯した場合と複数人で罪を犯した場合の違い
刑法の犯罪に関する規定は、ほとんどが一人で実行することを想定して犯罪になる行為類型と刑の重さが定められています。
一人で犯罪を実行した人を単独正犯ということもあります。
複数人が共犯として犯罪行為をした場合、刑法の共犯に関する規定を適用して、正犯または従犯として処罰されることになっています。
正犯は単独で犯罪を実行した単独正犯と同等の罪に問われますが、従犯は罪が軽減されます。 -
(2)実行していない犯罪も罪に問われる?
共犯として犯罪に関与した場合、どこまで刑事責任を問われるのでしょうか。
共犯の中でも主動的役割を果たした人や実行役が正犯とされるのは仕方ないとしても、それ以外の人は罪が軽くなると思われるかもしれません。
しかし、刑事裁判の実務では、かなり広い範囲で正犯として処罰されてしまうのが実情です。
また、共犯となる場合は、生じた結果の全部について罪に問われるのが原則です。
複数人が関与した犯罪は被害が大きくなりやすく、犯罪への関与の度合いが低いと考えていても、思った以上に重い罪に問われることがあります。 -
(3)民事上の責任はどうなる?
やや余談になりますが、複数人で犯罪を実行した場合の民事上の責任について解説します。
罪を犯して他人に被害を与えた場合、損害を賠償しなければなりません。
共犯者がいる場合、各人の賠償責任は被害者との関係では連帯責任となり、各人が全額の賠償責任を負うことになります。
この関係を民法で不真正連帯債務といいます(民法719条)。
つまり、被害者は共犯者の中で資力がある人から被害額全額を取り立てることも可能で、あとは共犯者間で責任の割合に応じて精算するということになるのです。
2、共犯にはどのような種類がある?
刑法の共犯に関する規定について解説します。
-
(1)共同正犯
二人以上が共同して犯罪を実行した場合は「共同正犯」となり、すべて正犯とされます(刑法60条)。
刑事実務で最も適用例が多い共犯の類型です。
共同正犯となる要件は次の点です。
① 自分の犯罪として実現する意思(正犯性)
単独犯であれば自分の犯罪として認識していることは明らかですが、共犯の場合は他人の犯罪に手助けのつもりで加担することもありえます。
そこで、犯罪に加担する動機や経緯、犯罪による利得、共犯者との関係性や役割を吟味して、自分の犯罪として実行する意思があるのかが判断されます。
後に解説する「教唆犯」や「ほう助犯」と区別される重要な要件です。
② 共謀の事実
共謀は、特定の犯罪行為について、共犯者と共同実行する意思をもって意思を連絡することをいいます。
事前に全員が集まって打ち合わせをする必要はなく、犯行直前に現場で共謀が成立することもあれば、共犯者AからB、BからCへと順次意思の連絡がある場合も共謀になります。
③ 実行行為
共謀に参加した共犯の誰かが共謀に基づいた犯罪行為を実行することで、共同正犯が成立します。
共謀の事実があれば、犯罪の実行行為をまったく分担していない共犯者も「共謀共同正犯」とされるのが刑事実務の考え方です。 -
(2)教唆犯
教唆とは、他人に特定の犯罪を実行する、決意を生じさせることをいいます。
犯罪を行う意思がない人を、そそのかして犯罪を実行させた場合は、教唆をした人(教唆犯)も実行した人も正犯として処罰されます(刑法61条)。
教唆行為は、「何か悪いことをやれ」というように漠然と犯罪を唆すだけでは足りず、特定の犯罪を実行する、決意を生じさせることが必要です。
また、教唆行為があっても実行役が教唆に基づいて犯罪を実行しなければ、教唆犯は成立しません。 -
(3)ほう助犯
ほう助とは、実行行為以外の方法で正犯の実行行為を容易にすることをいいます。
ほう助犯は、従犯として処罰されます(刑法62条)。
たとえば、強盗を計画している人に犯行に用いる車を貸した場合はほう助犯となる可能性が高いです。一方で、車を貸すから深夜に隣町でコンビニ強盗してこいとそそのかした場合は教唆犯となる可能性が高いです。
教唆犯と同様にほう助犯も、実行役が犯罪を実行しない場合、ほう助犯は成立しません。
従犯の刑は、正犯の刑を減軽することとされており(刑法63条)、罰則の上限と下限がそれぞれ2分の1減じられます(死刑に該当する場合は無期刑もしくは10年以上の有期刑、無期刑に該当する場合は7年以上の有期刑)。 -
(4)自殺を教唆・ほう助すると罪になる
自殺という行為自体は刑法に違反する行為ではありません。
しかし、他人を教唆して自殺を決意させたり、自殺を決意した人の手助けをしたりして自殺させた場合は、自殺関与罪(刑法202条)という犯罪になります。
自殺関与罪の罰則は、6か月以上7年以下の懲役または禁錮とされており、決して軽い罪ではありません。
なお、脅迫や虚言など不法な手段により精神的に追い詰めて自殺させた場合は殺人罪(刑法199条)になる可能性があります。
3、共犯の罪の重さはどのようにして決められる?
共犯がいる刑事事件では罪の重さはどのように決まるのか
- 一般的な刑事事件で考慮される要素
- 共犯者間の均衡として考慮される要素
の順を追って解説します。
-
(1)一般的な刑事事件で考慮される要素
刑の重さは、法律で規定された罰則の範囲で、犯情と一般情状という二つの要素によって決められます。
刑法の罰則は次のようにかなり幅をもたせて規定されています。
たとえば、- 殺人罪:死刑または無期もしくは5年以上の懲役刑
- 窃盗罪:10年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑
です。
そのため、罪の重さを決めるに当たっては、特に犯情が大きな判断材料となります。
① 犯情
犯情とは、犯罪事実そのものの内容に属し、あるいはこれと密接な関連を持つものをいい、次のような事情が考慮されます。- 結果
- 行為態様
- 動機
- 犯行に至る経緯
たとえば、窃盗の動機が遊興費ほしさの場合と生活苦による場合とでは、前者のほうが犯情が悪く、刑が重くなる要素といえるでしょう。
② 一般情状
一般情状とは、犯罪事実とは直接関係のない、いわゆる単なる情状の事実のことをいい、次のような要素が考慮されます。- 罪に問われた人の年齢や職業などの属性
- 被害弁償、示談の有無
- 反省の状況
- 被害感情
- 前科の有無
- 再犯防止の環境(監督者など)の有無
- 犯罪後の生活状況
罪の重さを決めるに当たって、まず犯情によって量刑の大枠を決定し、一般情状によってその大枠の中で調整が加えられるのが一般的な手順とされています。
しかし、一般情状の中でも、被害弁償、示談の有無や、前科の有無、再犯防止の環境の有無は大きなポイントとなります。
場合によっては、起訴されるか不起訴処分となるか、実刑か執行猶予かを分ける判断材料となることもあります。 -
(2)共犯者間の均衡として考慮される要素
共犯がいる事件では、次の要素も犯情として考慮され、共犯者同士で罪の重さに差がつくポイントとなります。
- 共犯者間の関係
- 主導的か従属的か
- 担当した実行行為
- 利得(分け前)の大きさ
なお、一般情状のうち、前科の有無や被害弁償への貢献度は、罪の重さを左右するポイントになります。
一般的な傾向としては、犯罪の重要な部分を担当した実行役や共謀を主導した人が主犯格として最も罪が重くなるといえます。
4、家族が共犯で逮捕されたら弁護士に相談を
刑事事件の弁護活動は着手が早いほど効果的ですが、共犯がいる事件は、
- 身柄拘束が長期化する傾向がある
- 示談が難しい
という特性があるため、弁護士による早期のサポートがより重要といえます。
以下、詳しく解説します。
-
(1)身柄拘束が長期化する傾向がある
共犯者がいる事件では、誰が主動的な役割を果たしたのかなど、共犯者間の役割分担が大きな焦点となり、各共犯者の供述が重要な証拠となることが少なくありません。
そのため、口裏合わせを防ぐために逮捕、勾留された上に、弁護士以外との面会や差し入れも禁止されることが多くなります。
弁護士は逮捕直後から面会することが可能で、家族などとの面会が禁止された場合でも不服申し立てをしたり、面会禁止の一部解除を求めたりする弁護活動を行います。
また、起訴されて刑事裁判になった場合、引き続き勾留される可能性があります。そのような場合にも、接見禁止の解除や保釈についての弁護活動を行います。
共犯事件の弁護経験が豊富な弁護士は、共犯事件で保釈の障害となる事由も熟知しています。
保釈が認められやすい条件を整えることを意識した弁護活動により、早期に保釈が認められることが期待できます。 -
(2)示談が難しい
被害者がいる事件では、被害弁償や示談が罪を軽くする大きな要素となります。
しかし、複数人が関与した事件では被害者が恐怖心を抱いていることが多く、本人や家族が被害者に接触することは得策ではありません。
また、被害弁償をするにしても、共犯者間の負担割合など民事に関する知識も必要になります。
弁護士は示談交渉など民事手続きの専門家でもあり、被害者の心情にも配慮した交渉のノウハウもあるため、適切な内容で示談を成立させることが期待できます。
5、まとめ
共犯がいる刑事事件では、犯罪の打ち合わせの場に居合わせたり、雰囲気に合わせて相づちを打ったりしただけで、実行役と同じ罪に問われる可能性があります。
積極的に犯罪を主導した場合だけではなく、いわば巻き込まれる形で重い罪に問われることもあるため、共犯として逮捕された場合は早急に弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所は刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が在籍しており、全力でサポートいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています