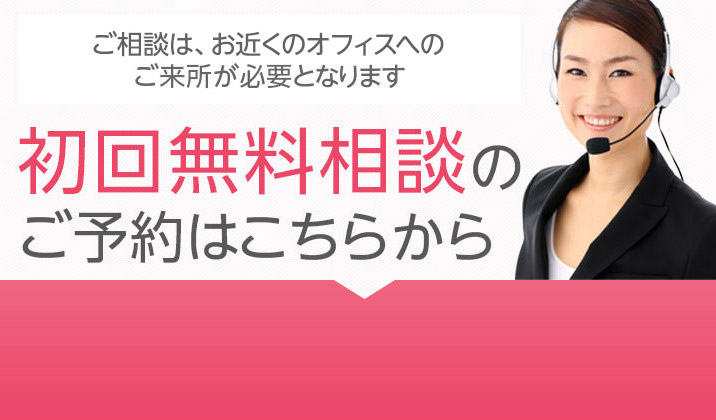元配偶者が財産分与を払ってくれない! 対処法はある?
- 財産分与
- 財産分与
- 払ってくれない

財産分与とは、離婚する際にこれまでの結婚生活で築いた夫婦の財産を分け合うことを指します。離婚時の話し合いにおいて、財産分与はトラブルに発展しやすい問題です。
どのような財産を分与の対象にできるのかわからない方もいるでしょう。また、離婚時に決めた財産分与を払ってもらえない場合、どのようにすればいいのでしょうか。
本コラムでは、財産分与として請求できる財産や払ってくれないときの対処法、強制執行について、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。


1、財産分与として請求できる財産とは?
財産分与とは、婚姻生活を送っている日々のなかで築いた財産を、離婚時や離婚後に分配することをいいます。
財産分与では対象となる財産と対象とならない財産があるため、確認してみましょう。
-
(1)財産分与の対象となる財産
財産分与では、夫婦が共に築いた共有の財産が対象となり、これを「共有財産」といいます。夫婦が共に築いた財産であれば、どちらか一方の名義で契約していたとしても、夫婦の共有財産となり、財産分与の対象です。
たとえば、現金や預貯金、年金、保険、退職金などの金融資産が対象です。また、土地や建物などの不動産、車など夫婦で共有するもの、一定の経済的価値のある貴金属や美術品も対象となります。株式や国債などの有価証券も共有の財産となるので忘れないようにしましょう。
ただし、婚姻期間前から所有していたもの、婚姻期間中であっても相続、贈与などにより一方が取得したものは、「特有財産」となり、基本的に財産分与の対象とはなりません。 -
(2)対象となるか不明な財産
共有財産となるのか判断が難しい場合は、共有財産と推定されることが、民法第762条2項で定められています。
-
(3)特有財産でも財産分与の対象となることもある
基本的に、特有財産は夫婦が共に築いた財産ではないので、財産分与の対象外です。ただし、以下のようなケースであれば、財産分与の対象となることもあります。
- どちらかが婚姻前に購入していたマンションに、夫婦で住み、その後ローンを2人で支払っていた
- 婚姻前に所有していた賃貸用アパートを、婚姻後は共同または配偶者が対応、管理し、アパートの修繕やクレーム対応などを行っていた
財産分与となりうるかの判断は「取得するときに支払いをした」「取得した後管理をしていた」「財産を使用する目的があった」などがポイントです。これらのポイントに合致すれば、通常であれば特有財産であっても、財産分与の対象となるケースもあるので注意しましょう。
- どちらかが婚姻前に購入していたマンションに、夫婦で住み、その後ローンを2人で支払っていた
2、元配偶者が財産分与を払ってくれない! 対処法はある?
離婚するときに決めていた財産分与を支払ってくれない場合、強制執行認諾文言つきの公正証書があれば強制執行することが可能です。しかし、公正証書を作成していない方もいるでしょう。
公正証書がない場合の対処法や公正証書・調停調書がある場合の対応について解説します。
-
(1)公正証書がない場合
離婚するときに公正証書の作成をしていなかった場合は、財産分与の回収を行うため「財産分与調停」を家庭裁判所に申し立てなければなりません。
調停によって財産分与の合意ができれば調停成立となり、合意ができなければ「財産分与審判」へ進み、財産分与の方法を裁判所が定めることになります。財産分与調停は、離婚してから2年以内であれば申し立てができますが、2年を過ぎてしまうと申し立てができなくなるので気をつけてください。 -
(2)公正証書や調停調書などがある場合
強制執行認諾文言つきの公正証書や調停調書があれば、「債務名義」として、強制執行するときに利用することが可能です。債務名義があれば、裁判所に強制執行を申し立てることにより、債務名義人の財産を差し押さえて、支払いをしてもらうことが可能となります。
しかし、いきなり強制執行することに抵抗を感じる方もいるでしょう。強制執行以外で支払いを催促する手段としては、内容証明郵便、履行勧告、履行命令があります。-
内容証明郵便
誰が誰に送ったのか、どのような内容だったのかを郵便局が証明してくれる郵便です。内容証明郵便を相手に送るときは、配達したことを証明してもらえる配達証明をつけることで、どのような内容をいつ配達したのか、郵便局に証明してもらうことが可能です。 -
履行勧告
家庭裁判所から義務者に対して、取り決めた義務の内容をきちんと履行するように勧告する手続きです。内容証明郵便と比べ、家庭裁判所からの勧告となれば、支払い義務者へのプレッシャーがさらに高くなると期待できます。ただし、履行勧告に従わなかった場合であっても、相手に支払いを強制する効果はありません。 -
履行命令
家庭裁判所から支払義務者に対して、調停や審判で決まった金銭の支払いをきちんと行うように命令する手続きです。正当な理由もなく従わなかった場合は、10万円以下の過料が科せられます。過料というペナルティーを加えることで、履行勧告より強い効果が期待できるでしょう。しかし、履行勧告と同様に、支払いを強制する効果はありません。
これらの手段を取っても支払ってもらえない場合は、強制執行を検討しましょう。
-
内容証明郵便
3、財産分与を払ってもらえないとき、強制的に差し押さえすることも可能?
支払いを催促しても、支払ってくれない場合は差し押さえを検討しましょう。差し押さえは、いわゆる「強制執行」のことで、調停や審判、裁判等で決まった支払いの義務がある者に対して、強制的に支払いを実行させるための制度です。
強制執行に必要なものや手続きの流れなどについて、確認していきましょう。
-
(1)強制執行に必要なもの
強制執行は、支払いを拒む者から財産を取り上げ、支払いをさせる非常に強い力を持った制度です。そのため、いつでも使える制度ではなく、使える状況や使うための条件があります。
必要なものや情報は、大きく分けて以下の3つです。- 判決や調書、公正証書など「債務名義」を証明する公的文書
- 差し押さえてほしい財産や相手の情報
- 強制執行の申し立てを行い裁判所の許可を得る
- 判決や調書、公正証書など「債務名義」を証明する公的文書
-
(2)強制執行の手続きと流れ
執行裁判所に強制執行の申し立てを行うためには、さまざまな書類と手続きが必要です。強制執行には「不動産執行」「動産執行」「債権執行」の3種類がありますが、今回はもっとも利用される「債権執行」の大まかな流れをご紹介します。
① 債務名義の用意
まず、債務名義を用意します。債務名義とは、慰謝料や財産分与などについて支払い義務を負う旨を記した、公正証書や調停調書のことです。債務名義がない場合は、家庭裁判所に調停、訴訟を申し立て、債務名義を取得する必要があります。
② 申立書の作成
次に、申立書を作成します。申立書には、債務者の住所や、どの財産を差し押さえてほしいのかを記載する必要があるため、あらかじめ債務者に関する情報をまとめておかなくてはなりません。また、申立書には原則、「執行文」の付された債務名義の正本を添付する必要があります。
③ 債権差押命令の発令・発送
裁判所が申立書等を確認後、問題がなければ債権差押命令が発令されます。差し押さえる旨が書かれた書面(差押命令正本)が債務者(強制執行の相手方)と第三債務者(差し押さえ対象になっている債権の債務者)に送達された後、債権者にも差押命令正本と送達証明書が送られてきます。
なお、第三債務者は、預貯金を差し押さえるのであれば銀行、給与を差し押さえるのであれば勤務先の会社が該当します。
④ 取立権の発生
裁判所から相手に差押命令が送達されてから、1週間を過ぎると取り立てることが可能となります。
なお、令和2年4月1日に施行された改正民事執行法により、給与債権が差押対象の場合、差押命令が債務者へ送達されてから4週間経過しなければ取立権が生じない特例が設けられました。ただ、養育費や婚姻費用のように、扶養義務に関する金銭債権の場合、この例外は適用されません。
4、財産分与に関する問題は弁護士にご相談を
特有財産と共有財産が混ざっている、財産を隠された、不動産の賃貸による収入があるなど、離婚に伴い財産分与の対象や金額を決めることは、難しいケースがあります。財産分与に関する問題をスムーズに解決するためには、弁護士への相談がおすすめです。
また、離婚した後、財産分与について相手が話し合いに応じない場合は、離婚後2年以内であれば、家庭裁判所に調停、審判の申し立てが可能です。調停手続では、共有財産の把握や、相手が隠している財産がないかなど、さまざまなことを調べる必要があります。弁護士に依頼することで、「弁護士会照会」という制度を使い、財産の有無を調査できる可能性があります。
5、まとめ
財産分与が支払われない場合は、強制執行認諾文言つきの公正証書を作成していれば強制執行によって財産の差し押さえが可能です。そのほか、支払いを求める方法としては、内容証明郵便による通知や家庭裁判所による履行勧告、履行命令を申し立てるなどの方法があります。
財産分与に応じない相手との話し合いや、強制執行に関する手続きを個人で行うことは難しいこともあるでしょう。離婚の実績豊富な弁護士に相談することで、財産分与についての適切なアドバイスが期待できます。財産分与をしっかり行いたい方、相手が応じてくれるのか不安な方は、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士へお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています