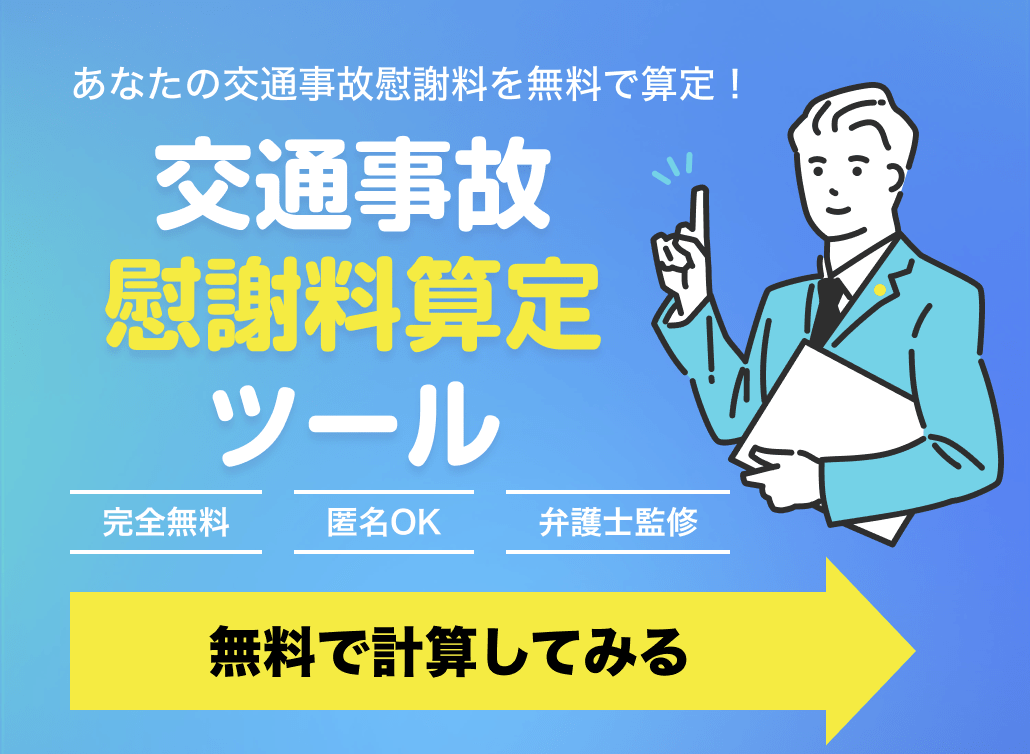交通事故加害者と連絡が取れないときの対処法|利用できる補償制度
- その他
- 交通事故
- 連絡取れない

静岡県警察浜松市警察部の公表によると、令和6年1月~12月までに浜松市内で発生した交通事故件数は4801件でした。
交通事故に遭った後、多くのケースでは加害者と直接連絡を取ることはなく、加害者側の保険会社と交渉を進めていくことになります。しかし、場合によっては加害者と直接連絡を取る必要があるケースであるにもかかわらず、連絡が取れなくなってしまうことがあります。そのような事態になれば、損害賠償請求の手続きに支障をきたすおそれがあることは言うまでもありません。
本コラムでは、交通事故加害者と連絡が取れない場合の対処法から、万が一連絡が取れなくなってしまった場合に利用できる補償制度、弁護士がサポートできることについて、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。


1、交通事故後、加害者本人と交渉しなければならないケースと注意点
交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、損害賠償に関する示談交渉を加害者本人と行わなければなりません。
その場合、加害者と音信不通にならないように、あらかじめ対策を行っておきましょう。
-
(1)加害者が任意保険未加入の場合、本人との交渉が必要
交通事故を起こしてしまうリスクに備えて、ドライバーの多くが任意保険に加入しています。加害者は被害者に対して損害賠償責任を負うところ、任意保険に加入していれば、自賠責保険ではカバーされない損害賠償を保険会社に支払ってもらえるからです。
加害者が任意保険に加入している場合、被害者から見た示談交渉の相手方は、加害者側の任意保険会社となります。
ただし、任意保険へ加入する場合は、保険料の支払いが発生します。そのため、保険料を節約したいなどの理由から、任意保険に加入していないドライバーも一定割合で存在します。
もし加害者が任意保険に加入していない場合、被害者は加害者本人と示談交渉を行わなければなりません。 -
(2)加害者と音信不通にならないためにすべきこと
加害者本人と示談交渉を行う可能性を想定して、加害者と音信不通にならないように、交通事故の直後から以下の対応を講じておきましょう。
① 加害者と連絡先を交換する
交通事故現場で加害者に話しかけ、氏名・住所・電話番号・メールアドレスなどを聞いておきましょう。
その際、連絡先の情報が正しいことを確認するため、身分証の提示を求めることも大切です。
② 警察に交通事故を報告する
交通事故の発生について警察に連絡すると、警察は事故現場で当事者の氏名・住所・連絡先・加入している自賠責保険などを確認します。
その情報がデータベースへ登録され、当事者は後に「交通事故証明書」の発行を受けられるようになります。交通事故証明書の内容を確認すれば、加害者についての情報を知ることが可能です。
なお、道路交通法第72条第1項により、交通事故の警察官に対する報告は義務付けられていますので、事故に遭ったら直ちに警察への報告を行いましょう。
2、交通事故の加害者と連絡が取れない場合の対処法
途中から音信不通になった、事故当時に連絡先を聴き忘れた、当て逃げに遭ったなど、何らかの理由で交通事故の加害者と連絡が取れない場合には、以下の対応を試みましょう。
-
(1)加害者が加入している任意保険会社に連絡する
加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社と示談交渉を行えばよく、加害者本人に連絡を取る必要はありません。
任意保険会社が判明していれば、加害者本人ではなく、任意保険会社の担当者に連絡を取りましょう。 -
(2)交通事故証明書を取得する
加害者が任意保険に加入していない場合には、加害者本人に連絡を取る必要があります。
警察に報告を行った交通事故については、「交通事故証明書」の発行を受けることができます。交通事故証明書には、加害者の氏名・住所・連絡先なども記載されているため、その情報を参照して加害者に連絡を取りましょう。
交通事故証明書の発行は、以下のいずれかの方法により申請できます。- ゆうちょ銀行・郵便局での払い込み
- 自動車安全運転センター窓口での申し込み
申請手続きの詳細については、自動車安全運転センターのホームページをご参照ください。
参考:「各種証明書のご案内」(自動車安全運転センター) -
(3)ナンバーから登録情報を調べる
当て逃げ・ひき逃げなどに遭い、加害者が不明である場合、何らかの方法で加害者を突き止めなければなりません。加害者の特定にながるもっとも有力な情報が、加害車両のナンバー(自動車登録番号)です。
事故現場の周辺に設置された防犯カメラや、ドライブレコーダーなどに記録された映像から、加害車両のナンバーが判明することがあります。ナンバーがわかれば、各地域の運輸局で「登録事項等証明書」の交付を受け、加害車両の所有者を特定することができます。
登録事項等証明書の交付を請求する手続きなどについては、各地域の運輸局にご確認ください。
参考:「登録事項等証明書交付請求」(関東運輸局)
お問い合わせください。
3、加害者が逃亡しても安心を! 政府保証事業による救済
もし加害者と全く連絡が付かず、任意保険どころか自賠責保険からの保険金も受け取れない場合には、政府保障事業による救済請求をご検討ください。
-
(1)政府保障事業とは?
「政府保障事業」とは、自賠責保険による救済の対象とならない人身交通事故につき、被害者の最終的な救済措置として、政府がその損害を填補(てんぽ)する制度です。
加害者が交通事故現場から逃走し、そのまま素性がわからなくなってしまった「ひき逃げ事故」などの場合には、政府保障事業による補償の対象となります。また、車検切れの車両が事故を起こした場合には同時に自賠責の保険期間が切れている場合も多く、この場合も政府保障事業の対象になります。
ただし、物損事故にとどまる場合には、政府保障事業による補償の対象外です。 -
(2)政府保障事業による補償の内容
政府保障事業では、以下に挙げるさまざまな損害項目について、自賠責保険に準じた補償が提供されています。
- 積極損害(治療関係費、文書料、その他の費用)
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 後遺障害慰謝料
- 葬儀費
- 死亡逸失利益
- 死亡慰謝料
ただし、健康保険や労災保険などから給付を受けられる場合、その金額は補償金額から差し引かれます。
政府保障事業によって給付された補償金については、後に加害者が判明した際、政府から加害者に対して求償が行われます。 -
(3)政府保障事業に対する請求方法
政府保障事業に関する請求事務は、政府から各損害保険会社に委託されています。
そのため、政府保障事業による救済を請求する場合、保険会社の中から1社を選択して、その窓口に必要書類を提出しましょう。
具体的な必要書類は、以下の国土交通省ホームページに掲載されています。
参考:「実際に事故に遭ったら?」(国土交通省・自賠責保険ポータルサイト)
なお、政府保障事業による救済を請求できるのは、以下のうち該当する期間に限られます。
交通事故から時間がたち過ぎないうちに、早めに請求を行ってください。- ① 傷害の場合:事故発生日から3年以内
- ② 後遺障害の場合:症状固定日から3年以内
- ③ 死亡の場合:死亡日から3年以内
お問い合わせください。
4、交通事故加害者が連絡を無視する場合に取り得る対応
加害者の連絡先はわかっているものの、加害者側が被害者からの連絡を無視し、示談交渉に応じない場合には、弁護士を通じて以下の対応を試みましょう。
-
(1)弁護士を通じて連絡を試みる
まずは弁護士名で内容証明郵便を送付し、加害者との連絡を試みることが考えられます。
弁護士から法的な根拠に基づいた請求を受ければ、加害者側も事態の深刻さを認識し、示談交渉に応じる姿勢を見せるかもしれません。もし加害者から返信があれば、その後の示談交渉も弁護士に一任できます。 -
(2)法的手続きを通じて損害賠償を請求する
加害者から返信がなくても、住所や氏名などの素性がわかっていれば、訴訟を通じて損害賠償を請求可能です。
裁判所に訴訟を提起すると、交通事故による損害賠償請求権の存否・金額について、公開法廷で審理が行われます。
加害者側が裁判所の呼び出しを無視して訴訟期日を欠席すると、最終的に被害者側の主張が全面的に認められます。
訴訟の判決が確定すれば、さらに裁判所へ強制執行を申し立て、加害者の財産から強制的に損害賠償金の回収を図ることもできます。
弁護士は、訴訟・強制執行の手続きを一貫してサポートし、被害者が適正額の損害賠償を獲得できるように尽力します。連絡を無視する交通事故加害者に対する損害賠償請求は、弁護士にご相談ください。
5、まとめ
交通事故被害者が加害者と直接交渉をするケースはほとんどありません、なぜなら、多くの方が任意保険に加入しているため、相手方が加入している保険会社の担当者と交渉することになるためです。しかし、交通事故の加害者が任意保険に加入していない場合、示談交渉は加害者本人と行うことになります。
加害者の連絡先は、交通事故証明書や加害車両の登録事項等証明書を確認すればわかることがあります。加害者と連絡を取る術がない場合には、政府保障事業への救済請求もご検討ください。
加害者の連絡先はわかるものの、連絡を無視されている場合には、弁護士を通じて損害賠償請求を行うことをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスは、示談交渉・訴訟を通じて、お客さまが最大限の損害賠償を獲得できるようにサポートすることが可能です。交通事故に関する損害賠償請求は、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています