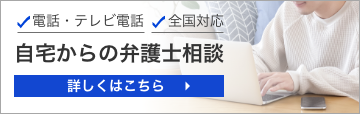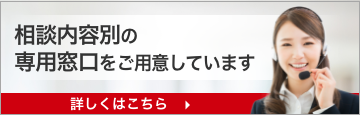不動産の瑕疵(かし)担保責任と契約不適合責任の違いを解説
- その他
- 不動産
- 瑕疵担保責任
- 契約不適合責任

静岡県の中でも多くの人口と広大な面積を持つ浜松市は、政令指定都市として大いに栄えています。しかしその一方で人口は年々減少しており、行政が空き家対策に取り組まなくてはいけない事態となっています。
近年は家族のあり方やライフスタイルも大きく変わり、年を取ってから単身世帯となる方もいらっしゃるでしょう。中には、今まで住んでいた家を離れてマンションに移り住み、不動産を売却してしまいたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
しかし、最近民法が改正されて売り主の責任が重くなったとの話もあり、何をどうすればいいかわからずに空き家を放置されている方もいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、不動産売却の際の売り主の責任と、民法改正のポイントと注意点について、浜松オフィスの弁護士が解説します。
1、不動産売買における瑕疵担保責任とは?
-
(1)瑕疵担保責任とは
以前の民法では、特定の物を売買する契約をした際、売り物に「隠れた瑕疵」があった場合は売り主が買い主に対して責任を負うことになっていました。これを「瑕疵担保責任」といいます。
「瑕疵」とは、当然あるものと考えられていた機能や品質が、売り物に備わっていなかった状態のことです。
瑕疵担保責任では、売り買いする物に最初からこのような隠れた瑕疵があった場合、買い主は売り主に契約の解除や損害賠償を請求することが可能となっていました。
ただし、買い主が隠れた欠陥につき何も知らず、注意をしていても知り得なかったという「善意」「無過失」であることが必要でした。改正民法では買主の主観は契約内容との適合性の判断の中で考慮されます。例えば、一定の欠陥があることを前提として売買価格を決めて契約していた場合に、欠陥の内容に契約適合性があるか否かが問題になります。 -
(2)不動産売買における瑕疵担保責任
不動産売買における瑕疵には、以下のようなケースが考えられます。
●土地を購入した場合
住宅用に土地を購入したが、土壌が基準値を越えた化学物質などによって汚染されていたため利用できないケースや、地上権などの用益権が設定されていて用途が限定される場合など。
●建物を購入した場合
新築住宅を購入したが雨漏りがする、手抜き工事で建物が傾いており開かない戸があるなど。
これらはいずれも、引き渡された不動産に瑕疵があったことによって買い主の目的が制約され、実現されないため、瑕疵担保責任が認められた場合は契約の解除、もしくは損害賠償請求が可能となっていました。 -
(3)瑕疵担保責任を請求される場合
買い主が瑕疵担保責任で損害賠償請求する際は、購入した物に瑕疵があると知らずに買った場合は、瑕疵の事実を知ったときから1年以内に請求を行う必要がありました。
なお、裁判になった場合には、買い主が- 具体的な瑕疵の内容
- それに基づく損害賠償請求をする旨の表明
- 損害額の算定の根拠を示すこと
を示し、売り主の責任を問う意思を、明確に相手に伝えなければなりませんでした。しかし、これでは買い主に負担が大きいため、その不均衡を是正するために民法が改正されたのです。
2、瑕疵担保責任と契約不適合責任は、何が違う?
新しい民法の規定では、「瑕疵」という言葉から「契約の内容に適合しない物」という言葉に改められ、売り主の責任がより重くなりました。
その他、具体的に大きく変わった点について説明していきます。
●特定の物に限らない
改正前は、特定の物の売買に限って売り主は責任を負いましたが、改正後は制約がなくなりました。
売り主が売った物の種類、品質または数量が契約内容に適合しているかが問われることになりました。
●売り主の責任の拡大
瑕疵担保責任の場合は、契約したときまでに生じていた瑕疵(原始的瑕疵)に限り、売り主は責任を負うとされていました。一方、契約不適合の場合は、引き渡すときまでに生じた瑕疵であれば売り主が責任を負う、と変更されました。
また、瑕疵担保責任の場合、売り主は買い主が契約時に知り得なかった「隠れた瑕疵」についてのみ責任を負っていましたが、その制約がなくなり、引き渡された物が、その機能を十分に果たすことができない場合は、売り主に責任を追及することができるようになりました。
このため、買い主が責任を追及する場合の、瑕疵を知らなかったことについて過失がない、という要件が消え、また意思表示も、必ず売り主に意思が伝わるようにするという厳しい条件ではなく、売り主に対して意思を伝える手段を取ればよい(売り主が、その連絡を見落としても条件を満たす)ことになりました。
●買い主の取りうる手段の拡大
これまでの契約解除・損害賠償に加えて、追完請求、代金減額請求ができるようになりました。この2点に関しては次の章で解説します。
3、契約不適合責任で買い主が請求できること
-
(1)追完請求
追完請求とは、買い主が売り主に対して、改めて完全な給付を請求することです。
数量が足りていなければ不足分を、品質が求めていた水準に達していなければその水準に合う物との交換を請求することになります。
建物などの場合は、別の物と交換することは難しいので、修繕請求をすることになります。 -
(2)代金減額請求
これは前述した追完請求ができない場合に認められる請求です。
買い主が建物の修繕を求めたが一定の期間を経ても売り主が答えない場合、あるいは、修復が不可能な場合は代金の減額を請求できるようになります。 -
(3)契約の解除
原則、引き渡された物の追完を要求しても、相手側から反応がない場合などには、契約を解除することができます。(これを催告解除と言います)契約の解除とは、契約の当事者一方がその意思により、初めからその契約をしなかったことにする行為です。
また、新民法では第542条において、以下の理由であれば、催告をしなくても契約を即時に解除できると定められました。
- 債務を全部履行することが不可能である
- 債務者が、契約内容を履行しない、と拒絶することをはっきりと表した。
- 債務の一部の履行ができない場合、または債務者が債務の一部を履行をしないと明確に表した場合で、履行をした一部だけでは契約をした目的を達せられないとき。
-
(4)損害賠償請求
契約が履行されない場合は損害賠償請求をすることができますが、新しい民法の規定では、売り主の帰責事由が必要となりました。
なお、以前は、契約を有効だと信じて支払った費用など、無効の契約を有効に成立したと信じたことによって生じた損害(信頼利益)のみが損害賠償の対象となっていましたが、民法改正後は契約が履行されていれば得られたであろう利益(履行利益)も損害賠償の対象となっています。
4、契約不適合責任の留意点とは?
民法改正によって、売り主の負う責任の範囲は格段に広がったといえるでしょう。
しかし、そのために不動産の売買をためらうことはありません。事前に十分な準備をしていれば、大きなトラブルになることを心配する必要はないからです。
-
(1)契約の内容を明確にし、契約書にはっきりと記すこと
契約不適合責任では、引き渡した物が用途を満たさない場合に売り主はそれらを補完する責任を負います。そのため、契約によって引き渡した物の性質をあらかじめ明確にしておくことで、過度な責任を負う事態を避けることができます。
たとえば、戸が壊れている建物を売る際は、その旨をしっかりと契約書に明記しておけば、修繕の責任を負うことはありません。
設備の不具合状況を書く書類である「付帯設備表」、設備以外の瑕疵を記載する書類「告知書」にも、しっかりと記載をしましょう。
また、引き渡しの方法についても明確に取り決めて契約書に記載して、確認しながらすすめていきましょう。 -
(2)瑕疵担保責任保険を活用する
瑕疵担保責任保険とは、物を他人に売った後で何らかの不具合が発見された場合、その補修費用の一部をカバーすることができる保険です。
契約不適合責任を問われた場合、追完請求をされる可能性が高くなりますので、万が一のためにも保険に入っておくことが得策です。 -
(3)弁護士に相談する
不動産の売買は金額が大きい取引ですし、土地や建物に関しては、登記や税金など特別な知識が必要です。
建築関係の専門家の協力はもちろんですが、スムーズな取引ができるよう、土地の売却の話が本格的になる前から、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は契約のプロですから、売却手続きの法的サポートはもちろん、不動産を売却した後、万が一のトラブルに発展した場合でも、代理人として頼もしい味方になることができます。
5、まとめ
民法が変わることによって、売り主の責任がどのように変わるのか、ご理解いただけたかと思います。
売り主の責任の範囲が広くなった分、買い主からクレームが入らないよう慎重に取引する必要があります。相手の主張によっては思わぬ重責を負うことにもなりかねないからです。
不動産を売りたいと考えた場合はまずは弁護士に相談しましょう。最初に売りたいと思う不動産に何か問題はないか、問題があった場合にはどのような準備をしておけばいいのか、問題が不動産の売買後にわかった場合にもどのように対処すべきか適切なアドナイスを受けることができます。
不動産の売却でお悩みの方はぜひ、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスまでお気軽にご相談ください。弁護士がスムーズにお取引できるよう、法的なサポートをいたします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています