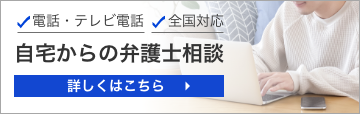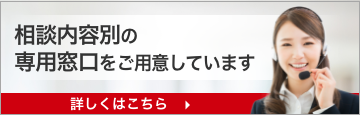従業員から訴えられた! 早期解決をするための方法とは
- 労働問題
- 従業員
- 訴えらえれた

毎月勤労統計調査のデータによると、静岡県内の事業所(事業所規模5人以上)における2022年8月の1人平均月間定期給与は25万4644円、名目賃金指数は100.8で、2か月連続で前年同月を下回りました。
会社(使用者)が従業員(労働者、社員)から訴えられた場合、会社側の責任を否定または限定するため、適切な準備を整えて対応することが大切です。対応を間違えると、多額の損害賠償やレピュテーション毀損のリスクを負うことになるので、弁護士へのご相談をおすすめします。
今回は、会社が従業員に訴えられた場合の対応などについて、ベリーベスト法律事務所 浜松オフィスの弁護士が解説します。
出典:「定期給与2か月連続で前年同月を下回る 毎月勤労統計調査地方調査結果(令和4年8月分)」(静岡県)
1、従業員から訴えられた場合における会社の初動対応
会社が従業員から訴えられた場合、できる限りダメージの少ない形で紛争を解決するため、以下の初動対応を行いましょう。
-
(1)反論の法律構成を検討する
会社としては、従業員の主張内容に合わせた適切な反論を検討しなければなりません。
よくある労使紛争の類型ごとに、会社として考えられる反論の例は以下のとおりです。(a)未払い残業代を請求された場合の反論例- 従業員の主張する残業が行われた事実はない
- 会社は残業禁止を従業員に周知していた
- 残業代計算の方法が間違っている
- 管理監督者に該当するため、残業代は発生しない
- 裁量労働制が適用されるため、残業代は発生しない
(b)不当解雇を主張された場合の反論例- 解雇要件を満たしている(たとえば懲戒解雇の場合、就業規則に定める解雇事由に該当すること)
- 解雇には客観的合理的な理由があり、社会通念上相当である(たとえば懲戒解雇の場合、再三の指導にもかかわらず全く素行が改善されないため、懲戒解雇が妥当であることなど)
(c)労災について損害賠償を請求された場合の反論例- 会社は労災発生防止のために十分な注意を払っていた
- 会社が十分な注意を払っていたとしても、労災の発生は避けられなかった
弁護士のアドバイスを受けながら、法的に説得力のある反論の構成を慎重に検討しましょう。
-
(2)会社の主張を基礎づける証拠を集める
会社が反論を行う際に、追加で何らかの事実を主張する場合には、その主張を裏付ける証拠を集めておくことが大切です。
たとえば、以下のような証拠を集めておくことが考えられます。(a)未払い残業代を請求された場合の証拠例- (残業禁止の指示を行ったことを主張する場合)指示を行った際の書面、メールなど
- (従業員が管理監督者に該当することを主張する場合)従業員の地位、勤務態様、待遇などに関する資料
(b)不当解雇を主張された場合の証拠例- (懲戒解雇を行う際に、再三の改善指導を行ったことを主張する場合)改善指導を行った際の書面やメール、過去の懲戒処分に関する資料など
- (整理解雇の適法性を主張する場合)経営危機の深刻さ、解雇を回避するために行った取組み、従業員向けに開催した説明会や面談などに関する資料
(c)労災について損害賠償を請求された場合の証拠例- (会社が労災発生防止の注意を十分払っていたことを主張する場合)会社が講じていた予防措置等に関する資料
主張内容によって準備すべき証拠が異なるので、弁護士に相談しながらできる限り有力な証拠を集めましょう。
-
(3)許容可能な和解ラインを設定する
会社としては、従業員との間の訴訟に対応するだけでも、多大な労力とコストがかかります。そのため、紛争の早期解決を目指す観点から、ある程度の水準で和解に応じることも一つの選択肢です。
民事訴訟の中では、裁判所は何度か当事者に対して和解を提案する機会があります。その際、和解案を受け入れるかどうかを適切に判断できるように、会社として許容可能な和解ラインを設定しておくとよいでしょう。
設定する和解ラインの水準は、経営者が会社の状況を総合的に判断して決定すべき事項です。ただしその際、法的な相場観・見通しを踏まえた上で決定することが望ましいため、弁護士のアドバイスを求めることをおすすめします。
2、従業員の訴えを無視したらどうなるのか? 会社が負うリスク
会社が従業員の訴訟提起を無視すると、従業員側の主張が全面的に認められることに加えて、会社としてのレピュテーションが毀損されるリスクを負ってしまいます。
-
(1)従業員の主張が全面的に認められる
民事訴訟では、「擬制自白」と呼ばれる制度が設けられています。擬制自白とは、当事者が口頭弁論において相手方が主張する事実を争うかどうか明らかにしない場合に、その事実を自白したものとみなす制度です(民事訴訟法159条1項)。
擬制自白は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合についても準用されます(同条3項)。そのため、会社が従業員による訴訟提起を無視して、答弁書などを提出しないでいると、従業員側の主張が全面的に認められてしまうのです。
従業員の主張を認める判決が確定した後、判決に従った金銭の支払いなどを行わずにいると、最終的には強制執行によって会社の財産が差し押さえられてしまいます。 -
(2)内部リークによってレピュテーションが傷つくおそれもある
従業員との間で適切に紛争を解決しておかないと、従業員本人やその周囲の人によって内部リークが行われ、紛争の内容などが報道されてしまう可能性があります。
紛争の経緯などについて会社に落ち度がある場合、レピュテーションの毀損は避けられません。その場合、売上の減少や新規採用への悪影響などが懸念されます。
レピュテーションリスクを抑えるためにも、できる限り従業員側の主張と誠実に向き合い、和解などによる解決を模索する方が賢明でしょう。
3、労働紛争を解決する法的手続きの概要・特徴
従業員との裁判外の交渉による解決ができない場合には、法的手続きによって紛争解決を目指すことになります。労働紛争を解決し得る法的手続きとしては、都道府県労働局のあっせん・労働審判・民事訴訟などがあります。
-
(1)都道府県労働局のあっせん
都道府県労働局では、紛争調整委員会によるあっせんが行われています。
参考:「個別労働紛争解決制度(労働相談、助言・指導、あっせん)」(厚生労働省)
あっせん手続きを主宰するのは、弁護士・大学教授・社会保険労務士などの有識者で構成された紛争調整委員会です。紛争調整委員会は、公平・中立な立場から意見の調整やあっせん案の提示などを行い、合意による紛争解決をサポートします。
労使間で何らかの合意が成立すれば、その内容に従って労使紛争は解決されます。
あっせん手続きは任意の合意形成に基づいて紛争解決しようとするもので、後述する労働審判や民事訴訟と違って紛争解決のための強制力は有していません。
労使間で合意が成立しない場合には、別の方法によって紛争解決を試みましょう。 -
(2)労働審判
労働審判は、労働審判官(職業裁判官)1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が主催して、地方裁判所において非公開で行われる法的手続きです。
参考:「労働審判手続」(裁判所)
実務上の運用としては、調停による解決に力点が置かれており、労働審判委員会はまず調停を試み、調停が成立しない場合には労働審判によって紛争解決の結論を示します。
労働審判の審理は原則3回以内に終了するため、迅速かつ柔軟な解決を期待できる点が大きなメリットです。
労働審判手続きの中で調停が成立すれば、調停条項に基づいて紛争は終局的に解決したことになります。審判によって結論が示された場合であっても、審判が出されてから2週間以内に異議がでなければ、審判は裁判上の和解や確定判決と同様の効力を有します。
ただし、審判に対する異議が出された場合には、審判の効力は失効して、自動的に民事訴訟手続きへ移行します。 -
(3)民事訴訟
民事訴訟は、裁判所の公開法廷で行われる紛争解決手続きです。当事者は、それぞれの主張につき証拠に基づく立証を行い、裁判所がその内容を総合的に考慮して判決を言い渡します。
民事訴訟で裁判所に主張を認めてもらうには、法的な根拠に基づいて説得力のある主張・立証を行うことが必要不可欠です。そのためには、弁護士と協力して充実した準備を整えることが求められます。
4、従業員とのトラブルについて弁護士に相談するメリット
未払い残業代・不当解雇・労災・パワハラなどにつき、従業員との間でトラブルになってしまった場合には、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
従業員とのトラブルをスムーズに解決し、会社にとっての損害を最小限に食い止めるには、従業員側の主張を踏まえた適切な反論と、法的な相場観を念頭に置いた落としどころの設定が重要になります。
弁護士は、会社が置かれている状況を踏まえた上で、会社にとってベストな方針・手続きの選択についてアドバイスします。従業員対応や法的手続きへの対応についても、必要に応じて弁護士が代行しますので、労力の大幅な軽減につながります。
労使トラブルにお悩みの企業経営者・担当者の方は、お早めに弁護士までご相談ください。
5、まとめ
会社が従業員から訴えられた場合、従業員側の主張内容を分析した上で、法的に有効な反論を多角的に検討することが大切です。会社として充実した準備を整えるためには、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
ベリーベスト法律事務所は、労使トラブルの解決を含めて、企業法務に関する経営者・担当者からのご相談を受け付けております。発生した労使トラブルへの対応にお悩みの方、日頃から相談できる顧問弁護士をお探しの方などは、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所へご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています